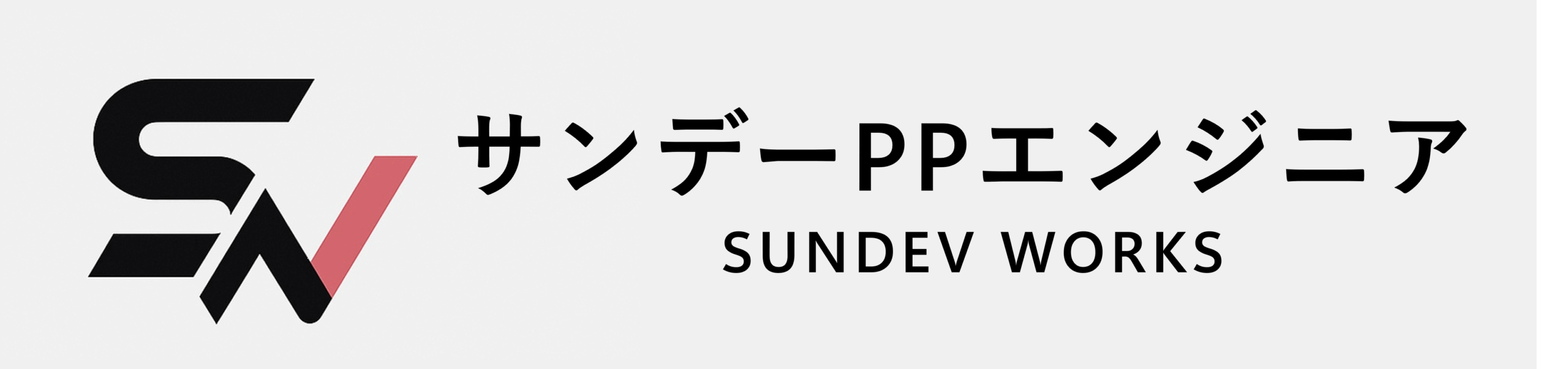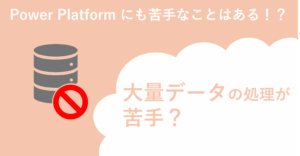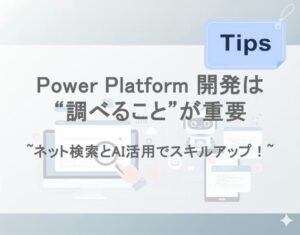Power Platformで既存の他社製品やツールの代替システムは開発できない
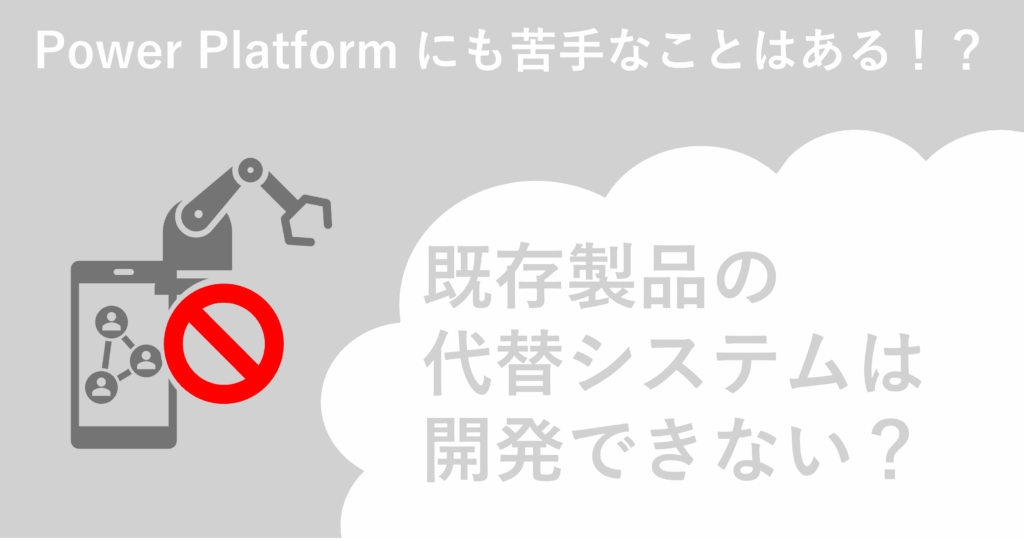
⚠️Power Platformは万能ではない!大規模なシステム開発に不向きな理由
最近、Power Platformでプロジェクト管理ツールや会計処理ツールを作りたいというようなご相談をよくいただきます。ローコードで簡単にアプリが作れるPower Platformに、大きな期待を寄せてくださる方が増えていることを嬉しく思います。
ただ、結論からお伝えすると、Power Platformは万能ではありません。
もちろん、業務効率化のためのアプリや自動化ツールを開発する上では非常に強力な味方になります。しかし、すでに世の中にある会計ソフトやプロジェクト管理ツールの代替として、Power Platformでゼロから大規模なシステムを構築するのは、ほとんどの場合お勧めできません。
今回は、なぜPower Platformがそういった大規模な開発には向かないのか、そしてどのような場面で真価を発揮するのかを、私の経験を交えながら詳しくお話ししたいと思います。
🚀Power Platformがもたらす「ローコード」の魅力
Power Platformの最大の魅力は、なんといっても「ローコード」であることです。専門的なプログラミング知識がなくても、マウス操作や簡単な関数を使って、業務アプリや自動化ツールを直感的に開発できます。
これにより、これまでIT部門に依頼していたちょっとした業務改善アプリを、現場の担当者自身が作成できるようになりました。
- 迅速なプロトタイプ開発: アイデアをすぐに形にできるため、フィードバックを素早く取り入れながら開発を進められます。
- コスト削減: 開発にかかる時間と費用を大幅に削減できます。
- 現場の課題解決: 現場のニーズに最も精通している担当者が、自分たちの手で最適なツールを作れるようになります。
このように、Power Platformは「市民開発」という新しい開発スタイルを広め、企業のデジタル変革を加速させる可能性を秘めています。
🚫「万能ではない」と断言する理由
では、なぜ私はPower Platformを「万能ではない」と断言するのか。
それは、「ローコード」であることのメリットが、大規模かつ複雑なシステム開発においてはデメリットに変わるからです。
1. 既存のSaaSや製品の代替にはならない
世の中には、プロジェクト管理、会計処理、顧客管理(CRM)など、特定の業務に特化したSaaSやパッケージ製品が数多く存在します。これらの製品は、長年の知見やノウハウが凝縮されており、あらゆるケースに対応できるよう緻密に設計されています。
Power Platformでこれらの機能をゼロから構築しようとすると、必要な機能をすべて実装するだけでも膨大な時間と労力がかかります。
例えば、会計処理ツールであれば、仕訳入力、勘定科目設定、月次・年次決算処理など、無数の機能が必要です。これらすべてをローコードで再現しようとすれば、結果的に「使えないもの」になってしまうリスクが高いのです。
SIerやコンサルにPower Platformを活用した業務改善、業務改革を依頼し、開発されたアプリが数か月後には使い物にならず、結局元の業務に戻る。あるいは、スクラッチ開発を依頼することは割とあります。
そういった失敗からDX化に悩むものの手動業務を続けられないというような相談もあります。
2. 強引な実装はかえってコスト高に
「既存の製品はうちの業務に合わないから、Power Platformでイチから作る」という考えは危険です。Power Platformはあくまで「ローコードツール」であり、制約の中で開発を進める必要があります。
例えば、大量のデータを扱う際に処理速度が遅くなったり、複雑なワークフローを構築する際に意図した通りの動作にならなかったりすることがあります。これらの制約を回避するために、無理やり複雑な実装を試みたり、追加のライセンスや外部サービスを導入したりすると、当初の予定をはるかに超えるコストがかかることがあります。
最悪の場合、せっかく作り上げたシステムが運用・管理できなくなり、開発期間もコストも無駄になってしまいます。こうしたケースは珍しくありません。
3. 大規模システム開発には「スクラッチ開発」が適している
もし、既存のSaaSや製品が自社の業務にまったく適しておらず、完全にカスタマイズされたシステムが必要な場合は、Power Platformのようなローコードツールではなく、「スクラッチ開発」を検討すべきです。
スクラッチ開発とは、プログラミング言語を使ってゼロからシステムを構築する手法です。費用も期間もかかりますが、その分、機能やデザイン、将来的な拡張性まで、すべてを自由に設計できます。
複雑な業務プロセスや大量のデータを扱うシステム、あるいはセキュリティやコンプライアンス要件が厳格なシステムには、スクラッチ開発が不可欠です。
スクラッチ開発で開発するほどのシステムをPower Platformで実現するとなると、結果的にスクラッチ開発より費用も期間もかかります。
💡Power Platformが真価を発揮する場面
では、Power Platformはどのような場面で活用すべきなのでしょうか?
それは、「既存の業務プロセスをよりスムーズにするための小規模なアプリやツール」です。
- Excel管理の脱却: 顧客情報や進捗管理をExcelで行っている部署に、共有可能なシンプルなアプリを導入する。
- 承認フローの自動化: 経費精算や備品申請のワークフローを自動化し、紙の申請書をなくす。
- 日報入力の効率化: 外出先からでもスマートフォンで簡単に日報を入力・提出できるアプリを作る。
- データ入力の支援: 既存の基幹システムへのデータ入力をサポートする、フロントエンドアプリを作成する。
このように、Power Platformは既存の業務の「すきま」を埋める、個人の業務を楽にする役割を担います。これにより、業務のボトルネックを解消し、社員の生産性を向上させることができます。
実際、毎日行う手動業務や雑務をちょっと自動化して、可処分時間を増やす、生産性を向上することを目的にPower Platformを活用している企業もあり、私は現状の最適解だと思っています。
🔮Power Platformの未来と可能性
もちろん、Power Platformは日々進化しています。CopilotをはじめとするAI機能の進化により、今後はさらに複雑なアプリも簡単に開発できるようになるかもしれません。
実際に自然な会話でシンプルなアプリやフローをAIが開発する機能は既にあります。
もしかすると、将来はローコード・ノーコードでありながら、まるでスクラッチ開発のように自由度の高いシステムが開発できるようになる可能性も秘めています。
しかし、それはまだ少し先の未来の話。現状のPower Platformは、大規模なシステム開発には不向きであることを理解した上で、賢く活用していくことが重要です。
🚀まずは触ってみよう!
この記事を読んで、「なんだか難しそう…」と感じた方もいるかもしれません。でも、一番の理解への近道は、実際に使ってみることです。
Microsoft 365のライセンスをお持ちであれば、Power Platformの機能(Power Apps, Power Automateなど)を一部利用できます。
ぜひ、身近な業務の「ちょっとした不便」を解消するアプリやツールを、自分で作ってみてください。百聞は一見に如かず、その可能性と制約を肌で感じてみることが、Power Platformを使いこなす第一歩になります。
何かご不明な点があれば、お気軽にお問合せください。
これからもPower Platformの活用法について、一緒に考えていきましょう!